
中学1年生で学習塾の夏期講習に行かせるか迷っているご家庭も多いと思います。特に最初のお子さんだと、どうすればいいのかわからなくて必要以上に考え込んで迷ってしまいます。
是非ここでの内容を参考にし、決めていただけたらと思います。
もくじ
中学1年生の夏期講習に勉強することとは
中学1年生が塾の夏期講習で勉強することは、復習がメインです。これは中学1年生に限らず、2年生、3年生になっても同じことです。では、どのようなことを復習するのでしょうか。
また、どのような子が夏期講習に行くべきで、どのような子には必要がないのでしょうか。
毎年5月下旬あたりから夏期講習のチラシが入り始め、6月には本格的に新聞折込チラシを賑わせてきます。7月になると駆け込みを狙ったチラシの文章も出てきますね。
行かせなきゃ!っと焦るのではなく、我が子に本当に必要か落ち着いて考えてみましょう。
中1夏期講習の数学で勉強すること
これはまず正負の数と言われる範囲です。中学生になると、小学生までと違い、負の数が出てきます。マイナスという概念ですね。簡単に慣れることが出来る子もいます。
しかしこのマイナスという概念がうまく受け入れられない子もいます。
わかることが当たり前ではありません。負の数というのは自然数ではありません。つまり自然界における数字ではないという考え方になります。リンゴがマイナス5個という言い方はないのです。
ですから、例として何かを考えるなら借金という考え方くらいしか出来ません。
これがどうしてもわからない子は、その子自身が一番つらく、頑張っているのです。
もしこの正負の数のところが全くわからないということでしたら、今後の数学がつまらなくなってしまう可能性が高いので、そうなる前に必ず対処が必要になります。
無料授業動画では配信済みなので、コチラを見ても理解が難しいようで、夏期講習を受けてみたいという意思が本人にあれば、是非お試し日数でも良いので行かせてあげて下さい。
-

正負の数の計算と数直線の使い方・考え方
中学1年生では最初に正負の数を学びます。この範囲はわかってしまえば、理解してしまえば何てことなくとても簡単なことなのですが、わからないうちは本当に難しく感じます。 わからないことは恥ずかしいことではあ ...
続きを見る
文字式の計算
数学は文字式の計算もすでに済んでいることと思います。これもなかなか難しいです。
中学1年生の前半のうちは、英語よりも数学の方が速いスピードで進んでいきます。
文字式と言えばa,b,x,yというようなアルファベットを含んだ項の計算になります。
この単元は、算数から数学へと一気に変わる範囲だと言えますので、子どもたちもすごく戸惑うところです。しかしこの単元は今後の中学校数学の土台となる部分ですので、非常に大切です。
ここの単元がつまずいたままだと、「文字」という概念がわからず、今後ずっと悩むことになると思います。実際に私も文字を理解出来ずに非常に苦労した経験があります。
こちらも動画は配信済みですので、これで理解が出来ないようであれば夏期講習も考えてみて下さい。もちろん完璧を求めるわけではなく、ちんぷんかんぷんでは困るという意味です。
-

中学1年生数学|文字式の計算がわからない子のための勉強法とコツ
私の自己紹介にあるように、私は文字式がさっぱりわかりませんでした。小学生の頃、算数は得意でしたし、嫌いでもなかったです。しかし、文字式の範囲は、算数から数学への過渡期。 ちょうど難しくなってくるので、 ...
続きを見る
中1夏期講習の英語で勉強すること
中学1年生の夏休みまでに勉強する英語の文法はそんなに難しいものではありません。しかし三単現のSという大ボスとも思えるようなものを習う学校も多いです。
まずはアルファベットを書けるようにすることと、読めるようにすることです。
大文字には慣れている子も多いですが、小文字がなかなか覚えられない子も多くいます。
特にbとdを反対に書いてしまったり、pとqが反対であったり、そもそもqがわからないという子もいますね。bとdのような間違いは、書き順さえきちんと覚えておけば起こりません。
bは縦の棒を先に書き、dはまるを先に書きます。
しかし両方とも縦の棒から書く子がいます。その場合、勢いでまるを書いてしまうことも多いため、思わず逆を書いてしまうなんてことが起こるわけですね。
アルファベットが思うように書けない状況であれば、夏期講習を考える必要があります。
もしくはお父さん、お母さんが教えてあげるのでもいいでしょう。
親子喧嘩に発展してしまわないよう気を付けて下さいね。
簡単な英語の文章を書く
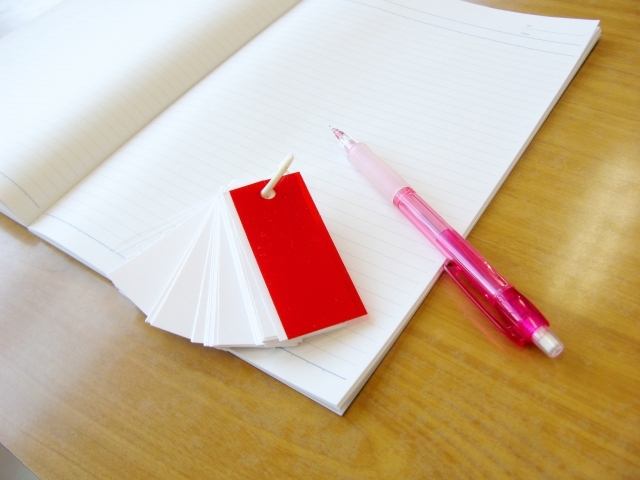
学校によってbe動詞の文、一般動詞の文のどちらが先になるか違います。
しかしどちらにしてもそこまで複雑なことはしません。
こんにちは、私の名前は〇〇です。
私は野球をします。
こういう簡単な文章になります。文章というよりも単語の連続で会話をするイメージですね。
そのため、そこまで難しさを感じることはないと思いますが、この文章の構成というのは、実はとても大切で、英語の基盤としてずっとついてくる部分になります。
後に習う難しい文章も、ほとんどがここで習う主語+動詞+目的語という構成を土台にして、そこに細かい装飾がされることで完成するものなのです。
ですからここで習うことはきちんと覚えておきましょう。
三単現のSを習う学校もある
すでに三単現のSを夏休み前に習った場合、もはや英語が大嫌いになっていたり、頭の中がパニックになってしまっている子もいるかと思います。
それほど中学1年生にとって三単現のSという単元はつらいものになります。
三単現のSというのは、本当に大切な範囲であるものの、多くの人がつまずきます。
そしてここでつまずくとテストの点数が本当に悲惨なものになってしまいます。
・・・・・・がっ!
その後は現在進行形、過去形、助動詞という範囲につながっていくので、実は三単現のSという考え方からは開放されるのです。つまり、つまずいた子がつまずいたままで終わらせてしまう危険性が大きいのです。
そうなると3年生になってから非常に苦労をします。
多くの子がつまずく場所なので、三単現のSが出来ないからと言って夏期講習が必須かと言われればそんなことはありませんが、少しでも理解は深めておいた方がいいかと思います。
三単現のSについては私も出来るだけわからない子の視点に立って解説しました。
-

三単現(三人称・単数・現在)のsで躓いた子のために
三単現のsは、中学生が英語で最初に躓くポイントです。このつまずきポイントですが、最初のつまずきポイントというだけでなく、最大のつまずきポイントでもあるのです。 そしてこの三単現のsは高校受験、卒業後も ...
続きを見る
中1で夏期講習に行くべきかどうか
別記事でも触れましたが、私の個人的見解としては、中学1年生の夏期講習に無理に参加する必要はないと思っています。本当にちんぷんかんぷんの場合は危険信号です。
確かに夏期講習は必要になるでしょう。
しかし、ちんぷんかんぷんでも、上記の授業動画などで「少しわかったかも」と思えるのであれば、必要ないのではないか、と思います。
それよりも部活や友達とプールに行くなど、楽しい思いで作り、そして学校の宿題をきちんと全て終わらせることの方がよっぽど大事だと思います。
真面目にテストを受けて数学や英語が20点に届かないようであれば危ないですが、それ以上取れている状況でご両親がパニックになる必要性は感じません。
それでも心配であれば、という感じでしょうか。
中1で夏期講習を受ける子とは
私が過去にアルバイトをしていた塾や、自分自身で経営していた塾での経験談です。
- 小学生の頃から塾に通っていた(そのまま夏期講習を受講)
- 兄弟、姉妹が通っている(同時受講)
- 学校の授業が物足りない(先取、予習が目当て)
- 学校の授業が全くわからない
こういう子が多かったです。
小学生の頃から塾にすでに通っている子や、兄弟、姉妹が同じ塾に通っていて、一緒に受けるというケースは一般的にもよくあることですが、それ以外で中1の夏期講習から入塾というのは多くありません。
良くも悪くも両極端な子が多かったです。
学校の授業だけでは物足りないので、上を目指すために中1の今のうちから高度な勉強をしたいと思うご家庭、もしくは上記で説明したように、ちんぷんかんぷんで困っているご家庭。
平均的か、それより少し上、少し下という状況であれば、前述のように思いで作り優先で構わないと思います。
夏休み明けへの心構え
中学1年生の英語は、恐らく一番難しいのは三単現Sなので、ここをきちんと理解出来てしまえばそれ以上に苦労することはないと思います。ですから繰り返し練習しましょう。
しかし数学に関してはまだまだ難易度がアップしていきます。
学校がわからない場合、ストップしてくれません。
わからないことが1つずつ増えていき、積み重なってしまうと学校の授業がつまらなく感じてしまい、問題を解くように当てられる(指される)ことが怖くなってしまったりもします。
こうなるとどんどん勉強が嫌いになっていってしまいます。
学校の定期考査(定期テスト)のみならず、小テストの結果や、学校の授業がわかるかどうかなど、ごはんの時に少し話題に出す形でもいいので時々気にかけてあげて下さい。
塾というのは、わからなくなった時が通い時という考え方もありますが、本人が行きたいと思った時こそ一番の通い時です。塾に行きたいと意思表示があったら、一緒に考えてあげて下さい。
当サイトでも出来るだけ多くの単元を、特に「わからない子」の視点に立って授業動画を無料で配信していきますので、勉強はあまり好きじゃなくてもパソコンやスマホには慣れている。
そういうお子さんは特に馴染みやすいかと思いますので、是非試してみて下さい。
最後に
中学3年生には、夏期講習は復習をする最初で最後のチャンスとよく言います。
しかし裏を返せば、中学3年生の夏休みはほとんどが夏期講習に使われ、総復習をすることになります。つまり、思い出を作る夏休みという意味では、中学1年生、2年生の方が向いています。
よほど必要性を感じているわけでなければ、「夏休み」を優先して下さい。


